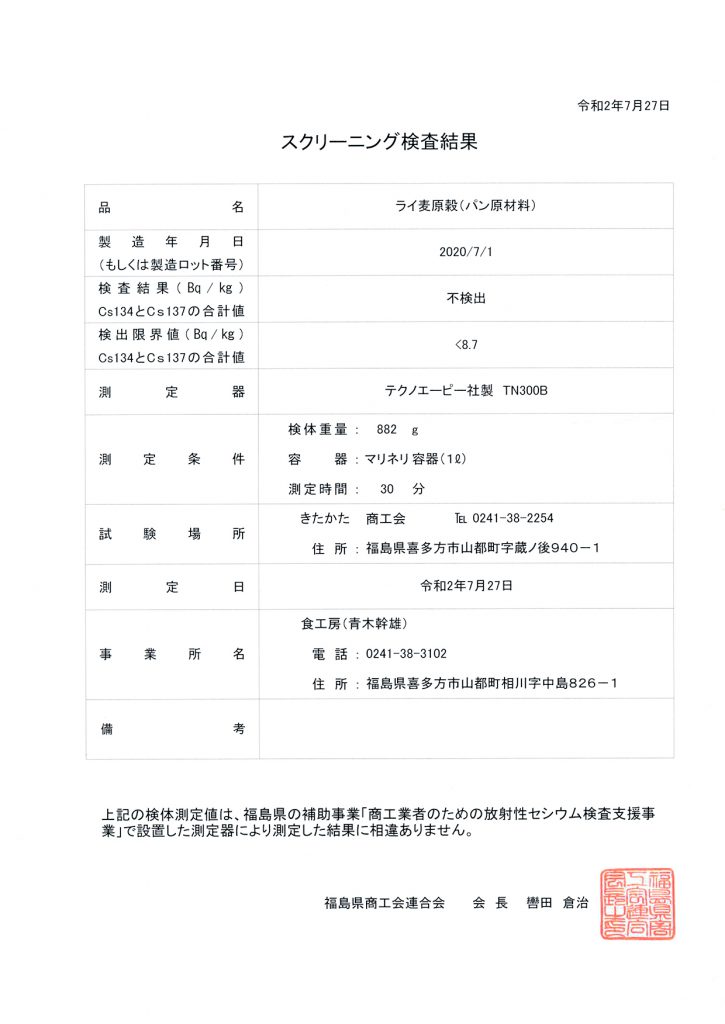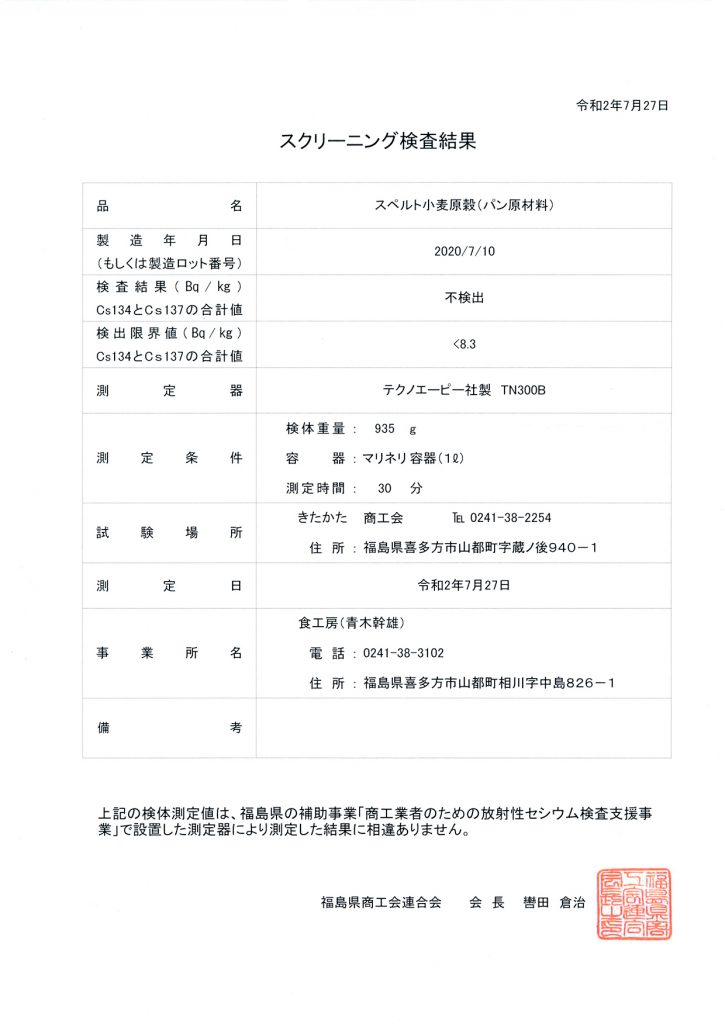麦畑の雪が消えて17日が経ち、麦たちも少しずつ再生して来ています。
ライ麦とスペルト小麦、そして南部小麦は、早くから越冬態勢を取って成長を止めていたので、順調に再生して来ています。
一方、デュラム小麦やライ小麦、そして試験栽培品種の幾つかは、昨年秋の暖かさに促されて成長し過ぎて一部茎立ちし始めていたものもあり、モシャモシャの状態で雪に潰されましたので、これからどんな具合に再生して行くものか、ちょっと掴みかねているところです。
今日は、とりあえず急を要すると判断してデュラム小麦に追肥を施しました。
グルテン(タンパク質)の含有量を上げるためには十分な栄養が必要で、特にタンパク質の素になる窒素が欠かせません。
昨年秋の過成長で、かなり地力を消耗しているようなので、即効性を重視して化成肥料を使いました。
化成肥料も、サプリメントみたいなものと理解していますので、時と場合によって躊躇なく用います。
もちろん基本は有機肥料です。
要は、おいしいパンが出来るところへ繋がればいいという話なので。
さてさて、明日はまた定休日明けのパン焼きの日です。
畑仕事も入れたので、今日一日の忙しかったことと言ったらありません。
おっと、もう寝る時間です。
ではでは。