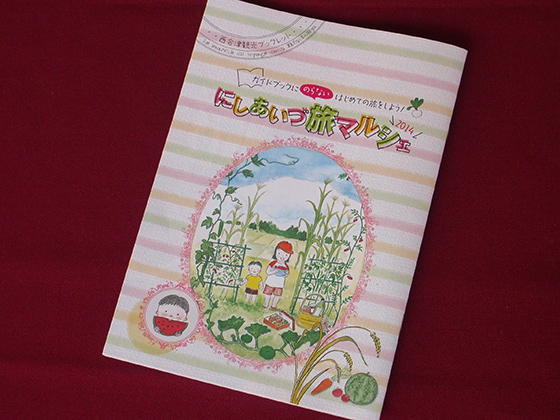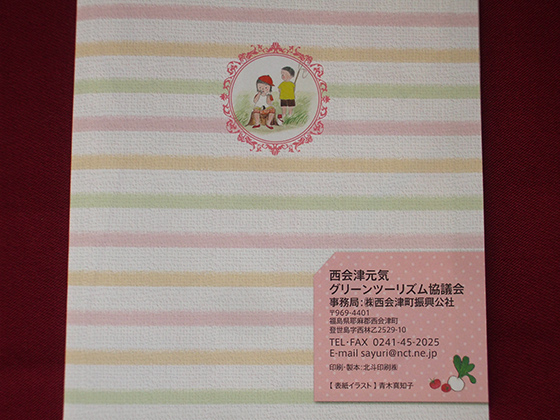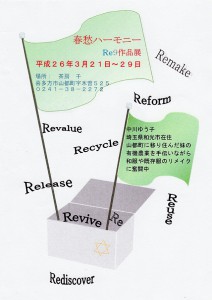このブログ「飯豊の空の下から・・・」には、2013年3月まで更新を続けていた過去バージョンがあります。
先日触れましたが、そのブログサービスがこの先終了と決まっており、ブログの移行がこれからの大仕事です。
どんな方法で、どこに移すことが出来るのか、ホストが用意してくれる移行のためのツール次第です。
他ならぬ私自身のために、何としても残したいものですから、今も時々読み返していますが、これから度々過去記事の再録をして行こうと思います。
移行が上手く行くなら、それは不要かも知れませんが、改めてこのページでもご覧いただきたいと思った時は迷わず再録して行きますので、どうぞお付き合いくださいますように。
それでは早速、今日は2010年6月6日の記事です。
土とITを活用せよ
2010.06.06
これから先の日本の社会の行く末を考えると、先ず今後この国の人口が増えることは、多分ないと思います。
と言うよりも、日本も世界も含めてこの地球環境は、もうこれ以上人口が増えることはもちろん、現在の状況にさえ耐えられないほどひっ迫しているのですから、今後の世界は、むしろ人口の減少を受け入れない限り、存続はあり得ないかも知れません。
いきなり話しが大上段になってしまいましたが、人口が減少するとどんなことになるのか、先んじてそれを経験しているのが、例えば私が住んでいる場所のような、地方の辺境に位置する地域です。
ものごとは、拡大傾向にある時は、何事も前向きに進みます。
将来に借りを作ることになるとしても、先に行けば行くほど楽に返せるのですから、何でも大きく計画する方向になります。
人々の欲望もいつの間にか肥大化して浪費はむしろ奨励される、それが今までの日本の社会の進んで来た道筋でした。
しかしどうやら、それももうお終いにしなくてはならなくなったようです。
資源やエネルギーの問題ももちろんありますが、少子化の問題は大方の人が想像しているよりもずっと根が深そうに思えるからです。
そのことについてはここでは触れませんが、どうしても人口減少が避けられないとしたら、私たちはどんな現実を受け入れなければならないのでしょうか。
私が住んでいる喜多方市山都町相川地区の、ここ数年の現状を思い出してみました。
私たちがこの地に移住してから早くも7年目になっていますが、その間に商店が2軒無くなり、水田耕作を止めた農家が数軒、重宝だった製材所が廃業(休業と言う話しもありますが。)、そして当地区にあった山都第二小学校が統合により閉校になりました。
こんな風に、人口減少がもたらすものは、それまであったものが無くなること、出来ていたことが出来なくなるという厳しい現実です。
そして、最終的に村落の維持が出来なくなる寸前まで追い詰められた地域を、「限界集落」と呼んでいます。
私の居るところなどは、その点ではまだまだ余裕があると言えますが、あと5年先10年先がどうだろうかと考えたら、決して楽観出来る状況ではありません。
さて前置きがすっかり長くなりましたが、それではこの先私が住んでいる地域のようなところは、何をどのようにすれば長らえることが可能でしょうか?
「土とITを活用せよ」とタイトルしたのは、ここにヒントがあると思ったからです。
この先ますます都会に人口が集中して、そこでの便利な生活だけは成り立つとしても、例えば食糧生産などは、相変わらず自然環境に依存しないわけには行かないでしょう。
ハイテク農業の開発で、土も日の光も要さずに工場で米や野菜が出来るようになるとしても、経済的にどうか知りませんが地球環境的に見れば、エネルギー収支はとんでもないマイナスで、全く非効率なやり方です。
逆に考えると、どうやらその一点にのみ地方の生き残りのチャンスがあるように思えます。
土は、全てを産み出しそして枯れることのない資源です。
もちろん、必要以上に収奪しないという、賢明なる選択が必須ですが・・・。
地方に、それも辺境と呼ばれる地に疎らに暮らしていても、ある意味豊かに幸せに生きていられる道はあると思うのですね。
そこで私がITを引き合いに出したのは、人の疎らな地域で孤立感を深めることなく過ごすために、ITはとても有効なツールだと思ったからです。
もちろんどんなものにも功罪があり、ITも犯罪の道具になったり、つまらない娯楽の手段に終始してしまう危険はありますが、それを言い始めたらキリがありません。最後は、やはり一人一人の問題ということになりますね。
いずれにせよ「土とIT」、とても重要なキーワードだという気がする私です。
そんな折も折、来年には喜多方市全域に光ファイバー通信網が整備されるとのニュースも伝わって来ています。
さて、この記事を書いてすでに4年近い歳月が流れました。
間には、震災もありました。
人口減少は、いよいよ現実の問題として認識され、社会の衰退にも正面から向き合わざるを得ない状況だと思うのですが、この国の人々は未だにぬるま湯から出られないようです。
覚悟も無いまま寒空の下に放り出される前に、自ら覚悟を決めて一歩を踏み出さなくては・・・。
地球環境的に見た「適正人口」ってあるのですね。
今日の再録記事には、まだ続きがあります。
近いうちにまたご覧に入れます。