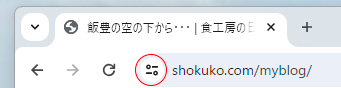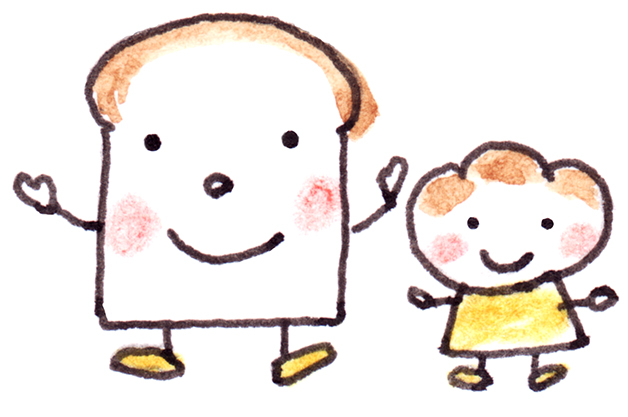食工房は今年1/8開業20周年を迎えます。
改めまして、新年あけましておめでとうございます。
食工房は、ただ今年末年始休業中です。
新年の営業再開は、1/11(木)からですが、その前に今年1/8に開業20周年を迎えます。
その節目に、皆さまのご愛顧への感謝の印として、いくつかの特典を用意いたしました。
以下にご案内いたしますので、お見逃しなくご利用ください。
通販ご利用の方
お買い上げ金額3,000円以上に対し500円割引のクーポンが適用されます。
適用期間は1月~3月末日まで、期間中何度でもご利用いただけます。
ご利用いただくサイト専用にクーポンコードを設定しましたので、それぞれそのクーポンコードを使用して割引を適用させてください。
★食工房オンラインストア~ rbkcsZa1fv
★ハンドメイドマーケット”Creema” ~ UWP5yH
※コード入力の際は、間違えないようご注意ください。
さらに、次回使用出来る送料無料クーポンも付与されます。
出荷完了後に送料無料クーポンコードをお知らせします。
次のご利用の際、3,000円以上のお買い上げに対し適用可能です。
サイトを利用せず直接食工房にご注文いただく場合は、納品金額から500円割引した金額を請求させていただきます。
また、ご注文履歴をこちらで把握していますので、次回ご利用分に対し送料無料を適用して請求させていただきます。
ご来店のお客さま
1月~3月末日までの間にご来店のお客さまに、3,000円以上のお買い物をされると、その場でいつでも使える500円分の食工房商品チケットを差し上げます。
さらに、期間中合計10,000円以上のお買い物をされた方に、1,000円分の食工房商品チケットを差し上げます。
20周年記念ビスケット
開業20周年を記念して、新しいビスケットを焼きます。
スペルト小麦100%の小麦粉と砂糖、ミルクやバターが原材料の優しい味のビスケットです。
形も、20周年記念のメダルの形になっています。
1枚ずつ個包装して、皆さまに無料配布の予定です。
定期便ご利用の方
定期便ご利用の方には別途サプライズを考えていますので、どうぞお楽しみに。
紙版・飯豊の空の下から・・・ pdfファイルを公開
やっとのことで、通信を出すことが出来ました。
まずは、web上に公開いたします。
印刷されたものも準備中ですので、店頭での配布あるいはネットをご利用でない方々のお手元にもお届けします。
多くの方にご覧いただければ、ありがたく幸いです。
「紙版・飯豊の空の下から・・・」No.76 2024年1月号をご覧いただけます。

★馬路村の柚子ジャムと柚子マーマレードが買えるようになりました。