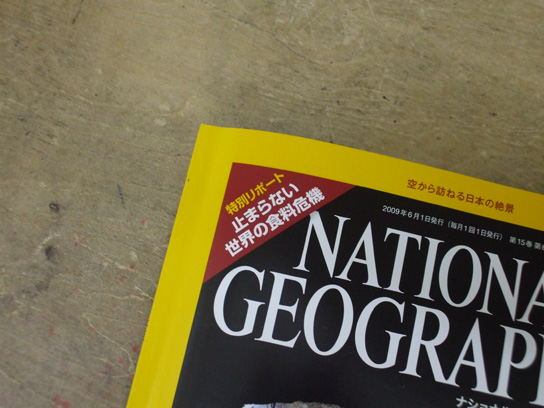ちょっと大きく出たなという感じのタイトルですが・・・。
まあお付き合いください。
先ず、デジタル技術の効用は何かと言えば・・・。
正確なコピーを、高速大量に作ることが出来る。
しかも、何度コピーを繰り返しても情報の質が劣化しない。
高密度の情報の保存が可能。
保存された情報の検索を、非常に高速に行える。
そして、このデジタル技術の実行に欠かせないのが、コンピューターです。
今やPCの普及で、コンピューターは私たちの日常に役立ち、またいろいろな側面で個々人の道具として、無くてはならないほどの存在になりつつあります。
とまあこんなことは、私が言うまでもないことかも知れません。
私がここで予感するのは、PCを使って作られ保存され蓄積された情報が、確実に私たちの物の考え方や人としての性格付けにまで、大きく影響を与えるようになるだろうということです。
何故そんなことを思うかと言うと、例えば記憶ということを考えてみてください。
私たち人間の記憶くらい当てにならないものはない、とよく言われますね。
いや実際、物事を正確に覚えていようと思うと、本当に大変です。
たいていの場合、今までだったら忘れたら困ることは、紙に書いておくとかしたわけです。
それでも、書いたものを失くしたり、書いたこと自体を忘れてしまうことだってありますね。
似たような出来事が交錯して、記憶の中身が入れ替わっていたなんてことも、そう珍しいことではありません。
そんな記憶の曖昧さも、場合によっては会話が弾むきっかけにもなり、あるいはまた争いの種になることもあったわけです。
この時代、それが画期的に変化していますね。
私たちは、公開されたデータベースを使って、十年前の今日が何曜日で、お天気はどうだったか、どんな出来事があったか、たちどころに明らかにすることが可能です。
そして個々人においても、データとして保存さえしておけば、何年何月何日の夕食に何を食べたか、その時誰かお客さまがいたかどうかなど、そんな詳細なことまでも瞬時に引き合いに出せるのです。
これからは、「そんなことは覚えていない。」と言い訳しても、サッと証拠を見せられて尻尾をつかまれるということになりますね。
そういう意味で、何事も正確を期そうと思えばいくらでもデータを出せる状況が、段々実現しつつあるわけです。
私たちの多くが、毎日あるいは時々でも、こうしてブログを書いて、時には写真入りで、こうしたデータがどんどん蓄積されると、それを記憶の道具として使うようになります。
実際私も、過去の記事を見て記憶を新たにするということが、度々ありますから。
そうです。
このPCシステムは、人間の脳に対しての外付けディスクの役割を果たすようになりつつあるのではないでしょうか。
私たちは、極端な話、物事の詳細な記憶の大半をPCに入れて、入れたということだけ覚えておけば良いことになるのではないか。
その時興味の湧かないことは、安心して忘れてしまえる。
そして必要な時には、正確な情報をすぐに提示出来る。
そうなると、人の頭の使い方も変わってくるのじゃないかと思うのです。
どんなふうに・・・かは、いろいろ想像が巡ってまとまりませんが、何か人類の本質に関わるような変化が起こりはしないか?と、そんなことを考えてしまう私です。

4ギガバイトのUSBフラッシュメモリー
ほぼ毎日書いている、このブログ2年分のデータが100MBにも達していませんから、
このメモリーの中には優に80年分のブログ記事が収まってしまいます。