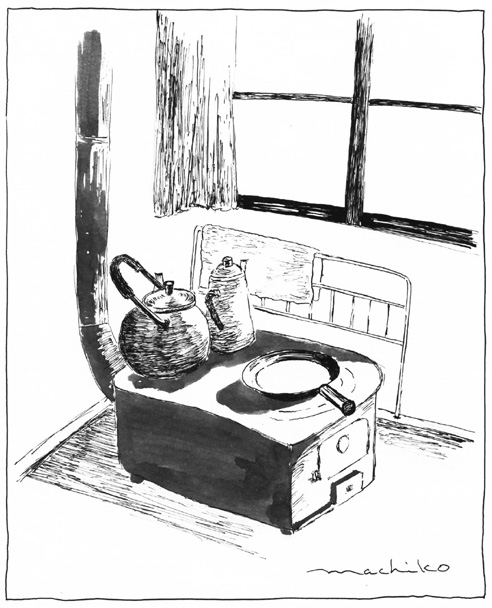マムシグサの雌花
今日も忙しい一日を過ごしました。
途中、毎年今頃、裏の林の中の土手に花を咲かせる「人」のことが気になって、15分間だけと決めて、長靴を履いて入って行きました。
まだ時期が少し早かったようで、つぼみは葉に包まれていました。
でも、去年よりは確実に数が増えたようで、嬉しい気持ちで立ち去ろうと振り返ったところ、別な「人」がこちらを見ていました。
山暮らしをしていたころにも、家の周りでよく見かけた、特別存在感の濃いその「人」の名は「マムシグサ」。
決して美しいというわけでなく、どちらかと言えば気味悪がられそうな姿です。
初めてこれを見た時は、本当に気味悪く恐ろしい感じがして、草刈り機で狂ったように刈り倒したものです。
でも長年見慣れたせいか、この頃は親しみさえ感じるようになりました。
何だか「魔法使い」のイメージなのです。
マムシグサはサトイモ科の植物で、多くの人が愛でて止まない「ミズバショウ」の仲間です。
それにしては何という違いでしょう!
ほとんど人に顧みられることもなく、暗い林の中で、あちらに一本こちらに一本と、群れになることなく花を咲かせる姿に、私は妙に心を動かされました。
「美」とは、一体何なのか・・・?
一時、そんなことを考え込んでしまいました。
お知らせ
ゴールデンウィーク中、4月29日(火)、30日(水)は定休日で、店はお休みです。
また5月6日(火)もお休みします。