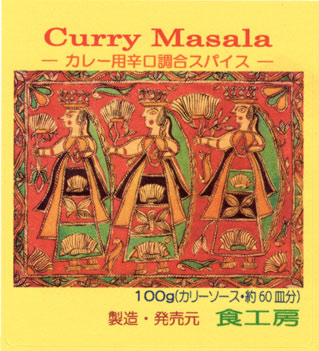小麦色とは、まさにこの色合いのことです。本当に美しいと思います。
先日、当山都町内の農家の方から、小麦があるので食工房で原材料として使ってみませんか、というお申し入れをいただいていました。
今日、その方が小麦原穀と自家製粉した小麦粉を持参して、わざわざご来店くださいました。
今日、とりあえずサンプルにいただいたのは、「あおば」という品種です。
業界の方なら良くご存知のはずですね。
国産小麦の中では、比較的製パンに向いているとして、一頃もてはやされたこともある小麦です。
その方は、私などよりずっとお若い方ですが、地域の農業の行く末を真剣に悩んで、いろいろ考えていらっしゃる方です。
小麦の栽培も、遊休農地が荒れ放題になっている現状を、見るに耐えないお気持ちから思い立たれたそうです。
小さなパン屋の食工房が、地域の農業の将来に果たしてどの程度貢献出来るか分かりませんが、少しでもこの小麦を役に立てられる方法を考えたいと思っています。
さし当って、全粒粉に自家製粉出来ますので、早速現在使っている粉にブレンドして、何種類かパンを焼いてみようと思います。
地元の原材料で製品が出来ることは、以前から私が望んでいたことでもありますので、今後山都産小麦のパンがメニューに乗ることは、これでほぼ確実となりました。
どうぞ皆さま、今後の取り組みにご期待くださいますように。
おしらせ
Blue Lace の黒田真理さんの服、入荷しました。
☆麻100%のちよっと短かめゆったりパンツ
☆綿・麻混紡のブラウス、チュニック
☆麻100%のスカーフ まりさんが、丁寧に横糸を抜いて作ったフリンジがとてもきれいです。
※例によって、気になる方はお早めにご来店ください。