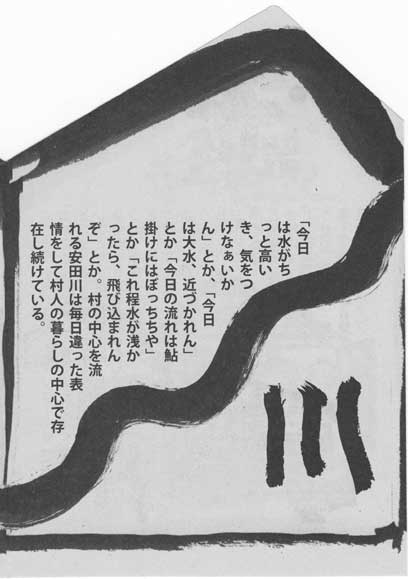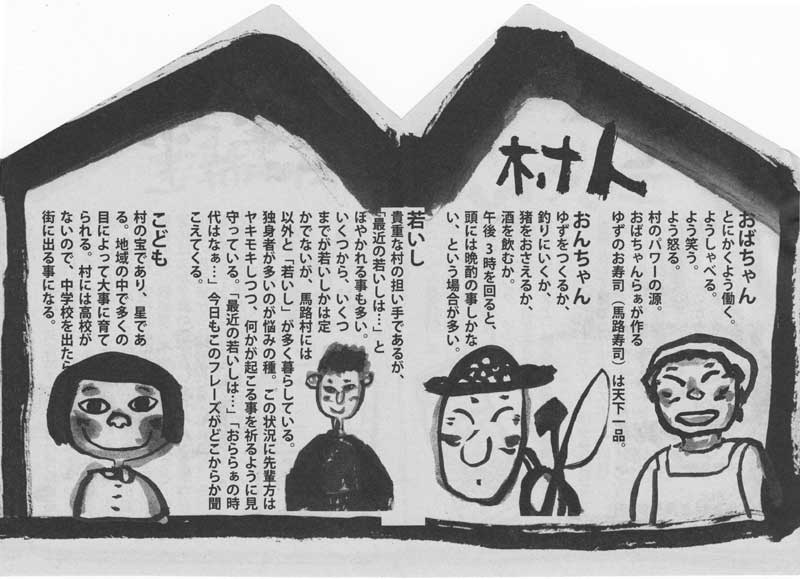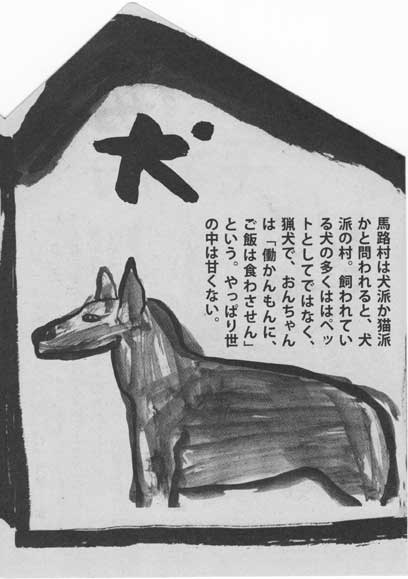※本日、長文になつております。最後尾に、食工房よりお知らせを掲載しております。
昨夜(1月31日)、TVで「NHK特集・無縁社会」という番組を見ました。
今この国で、誰にも看取られず孤独死する人が年間3万2000人。
自殺者の数と同じだと言われます。
その番組の中で浮かび上がって来たのは、人が社会との接点を失って生きる無縁社会というものでした。
さて、日頃テレビを見ることのない私が、何故その番組を見ることになったかと言うと、この会津に昭和村というところがあって、そこにお住いの佐藤さんという方のブログ「佐藤孝雄のじねんと録」1月31日(昨日です。)の記事<参照>の中に告知されていたからです。
そして、このブログ記事の中でも触れられている「雪の墓標」は、その昭和村の佐藤さんがお住いの地区を舞台に、NHKが取材制作し1993年4月30日に放映した、ドキュメンタリー番組のタイトルです。
奥会津の豪雪地帯、福島県昭和村。
冬、見渡す限りの雪原に、4メートルほどの棒くいが立てられている。
これは、家々の長男が、父母の死が近いことを察し、晩秋、墓が雪で埋もれないうちに立てておいた墓のしるし、雪の墓標である。
番組では、昭和村に生きづいている日本古来の伝統的な葬送の儀礼を、村の最長老の葬儀を中心に克明に記録する。
※NHKアーカイブス保存番組詳細資料より
残念なことに当時の私は山暮らしの最中で、この「雪の墓標」の放映のことは知る由もなく、またテレビもありませんでしたから、見ることは出来ませんでした。
しかし、地方の寒村の村人たちによる葬儀の様子は、この私には十分想像することが出来ます。
大分前のことになりますが、私は、ある地方の寒村で村人だけで執り行う葬儀に、二度ほどかかわったことがあり、そのうちの一度は、仏様を埋葬(土葬)するための墓堀りもさせていただきました。
そこは雪国ではありませんでしたが、これが豪雪地帯でのことなら、どれほどの労苦を伴うことか想像に難くありません。
お年寄りが亡くなるのは、往々にして寒い冬の時期が多いのです。
今はほとんど火葬にするので、そんな苦労は無くなったかも知れませんが、除雪車も重機もない時代に、墓に辿りつくだけでも大変なのに、数メートルの雪の下の墓を掘り出して、さらにその下に亡骸を埋める穴を掘らなくてはならないのですから、弔いを出すことは、周りの人々全員の助けを借りなければ到底成し遂げられることではありません。
人は死んで後も、こうして大勢の人にお世話になるのだと、それが分かっているから、自ずとそれは生き方にも関わってくるということになります。
集落の人々全員が家族のように濃密な付き合いをするのは、こうした苦労を分かち合っているからだと、私は想像するのです。
一方時代は下がって今、インターネット上には、趣味を同じくする人たち、気の合う仲間、同じ主義主張に盛り上がる人たちが簡単に出会えるようになり、バーチャルなコミュニティーが無数に生まれています。
現実の生活を煩わされることのない、こうした軽く緩やかな関係を歓迎する風潮は、近年益々顕著になって来ています。
しかし、自分の周りをお気に入りだけで囲って、気に入らない関係は全て遠ざけて生きるそんな傾向は、本当の社会性が育まれるためにはむしろ有害だと指摘する識者もいるのですね。
私にも、ただそれは無縁社会の裾野のようにしか見えません。
対立するものと折り合いを付け、意見の食い違いを克服し、争う相手と和解する道を探ることこそが、本当の社会性であり、平和への道筋に違いないからです。
そして家族という逃げ場のない人間関係は、実はそれを学ぶための教室なのだと、私は自分の家族を持った時以来ずっとそう思って来ました。
でも本当を言うと私は、一人でいることも嫌ではありませんし、孤独に生きることがすべて悪いとも思いませんが、どうやら人は最後まで孤独なままではいられないようだと、番組を見ていても感じたことです。
では何故このような社会が出現したのでしょうか。
それは、昨日今日に原因を探しても、誰も何も理解することは不可能だと思います。
50年あるいは100年の時間、つまり二世代、三世代さらに四世代の間の私たちの社会の流れ、また世界の潮流という外面的な理由ももちろんあると思います。
そしてまたその長い時間に、私たち一人一人が何を目指し、何を良しとし、何を望んで過ごして来たかという、内面的な理由もあるでしょう。
その両方がどちらが先と言うことはなく、複雑に影響し合って今の社会が出来上がってきたのだと思います。
いずれにせよ、そんな長い時を経て成って来た結果を、小手先で動かすことは不可能です。
昔は自分たちで弔いを出していた多くの地域でも、今ではお金さえ出せば斎場で立派な葬式が出来て、煩わしい思いをしなくて済むようになったと喜んでいる場合が多いのですから、そのようにして少しずつそして確実に人の縁は解体されつつあるのです。
一体何がそうさせているのか?
仕事でしょうか、お金でしょうか、人の欲望でしょうか・・・。
「雪の墓標」と「無縁社会」の間にある隙間を埋めるには、やっぱり50年あるいは100年かかるでしょうか。
今の世の中に、少なからぬ違和感と一種言いようもない哀しみを、どうしても自分の中から消し去ることの出来ない私です。
食工房よりお知らせ
今週のクッキーは、バタービスケット、わらいごま、ジンジャークッキー、ナッツクッキーです。
他に、新製品「くるみびすけっと・エダムチーズ入り」340円が新発売になります。
マフィンは、ココリスとスィートハートです。