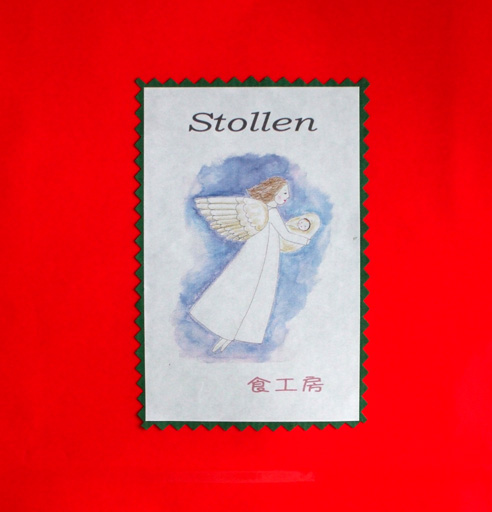父が亡くなって以来13年間、だいたい毎年一回、高知の実家に出かけています。
高知に行くと、いつも決まってこの豆腐を買って来て食べます。
近くのスーパーマーケットで、当たり前に売っています。
そしてけっこう良く売れているみたいで、売り切れていることも珍しくありません。
写真で分かるとおり、パックに入っていません。
そのままポリ袋に入っています。
下の方に水分が、半分くらいしか溜まっていませんね。
袋から出す時は、上から鷲づかみして持ち上げても大丈夫です。
うちの長女は、包丁でこの豆腐を切る時、チーズみたいだと言ったものです。
かたくてキッチリ中身が詰まったこの豆腐、大豆の味をすごく濃厚に感じます。
それにかたいと言っても、決して食感が悪いわけではありません。
とにかくうまい豆腐です。
高知に居る間、ほとんど毎日、毎食、この豆腐を食べています。(まるで豆腐の食い溜め・・・!)
お値段は、たしか1個98円。
半丁と表示されていますが、十分普通のパック入り豆腐一丁分に勝るボリュームがあります。
私は、以前豆腐も手づくりしていたことがあり、約15年間、豆腐は買わずに自家製のを食べました。
大豆と天然ニガリだけでつくったその豆腐と、今高知でお目にかかるこの豆腐は、同じ味、同じ食感です。
かたくて中身が詰まっているということは、同じ豆腐一丁をつくるのに使う大豆の量がずっと多いということです。
当然、濃厚な味がするわけです。
揚げ出し豆腐などは、水切りなしでOKです。
ちなみに、この豆腐をつくっている豆腐屋のホームページがあります。リンクは<こちら>
念のため申し上げておきますが、高知の豆腐は皆かたいというわけではありません。
やわらかい絹ごし豆腐も売っています。